-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
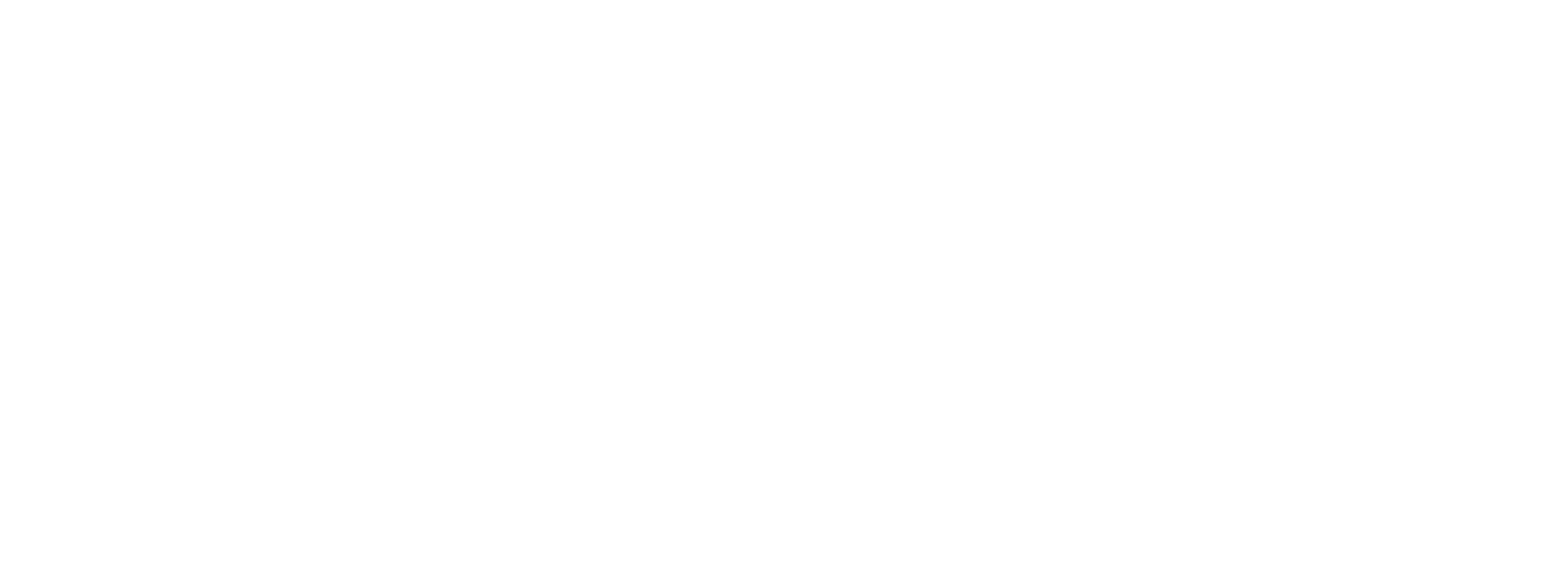
皆さんこんにちは!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っている
増田工業、更新担当の富山です。
目次
防水工事の中でも代表的で、多くの現場で採用されているのが「ウレタン防水」です。
液状のウレタン樹脂をローラーやコテで塗布し、乾燥させることでゴム状の防水膜を形成します。
継ぎ目のない仕上がりが得られるため、雨水の侵入経路をつくらず、長期にわたって建物を守ることができます。
液体を塗り広げる工法なので、凹凸のある複雑な形状や排水口まわり、立ち上がり部分などにも施工しやすいのが特徴です。シートを貼る工法と違い、細かい部分にもきっちり対応できます。
乾燥するとゴムのような弾力性のある膜が形成され、建物のわずかな動きや温度変化による伸縮にも追従します。これにより、経年劣化で起こる小さなひび割れや揺れによる損傷にも強い耐久性を発揮します。
下地処理:既存の防水層やコンクリート面を清掃・補修し、密着を高める。
プライマー塗布:下地とウレタンをしっかり接着させるための下塗り材を塗る。
ウレタン樹脂の塗布(1層目):ローラーやコテで均一に塗り広げる。
乾燥後に2層目を塗布:膜厚を確保するため、通常は2回以上塗り重ねる。
トップコート仕上げ:紫外線から保護するために表面にトップコートを塗布。
この流れを経て、均一で継ぎ目のない防水層が完成します。
複雑な形状に対応:シートでは難しい排水口や段差も問題なく施工可能。
継ぎ目のない仕上がり:シームレスで雨水の侵入口が生まれない。
弾力性が高い:地震や熱膨張など建物の動きに追従できる。
改修工事に強い:既存の防水層を撤去せず「重ね塗り」ができる場合が多く、工期とコストを抑えられる。
施工技術に左右されやすい:膜厚が均一でないと耐久性が落ちる。
乾燥時間が必要:完全硬化までに数日かかり、天候に左右されやすい。
紫外線に弱い:トップコートで保護しないと劣化が早まる。
このため、ウレタン防水は定期的なトップコート塗り替え(5〜7年ごと)が推奨されています。
ベランダやバルコニー
屋上や廊下などの歩行可能な場所
凹凸や複雑な形状を持つ施工部位
戸建て住宅からマンション、商業ビルまで幅広く使われる汎用性の高い工法です。
ウレタン防水は、柔軟性と施工性に優れた万能な防水工法です。
複雑な形状でもシームレスな仕上がりを実現でき、改修工事にも強いのが魅力です。
ただし、耐用年数を伸ばすには定期的なトップコート更新と、熟練した職人による確実な施工が欠かせません。
次回もお楽しみに!
増田工業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っている
増田工業、更新担当の富山です。
目次
防水工事には複数の工法があり、施工対象や環境条件に応じて使い分けられます。
ウレタン防水:液状のウレタンを塗布し、防水膜を形成。複雑な形状に対応可能。
FRP防水:ガラス繊維を混ぜ込んだ強靭な防水層を形成。軽量で耐久性が高い。
シート防水:塩ビやゴムシートを貼る工法。施工が早く、大面積に有効。
アスファルト防水:歴史ある工法で強度が高い。ビルや公共施設で採用。
セメント系防水:密着性が強く、地下や水槽などで用いられる。
防水工事は以下の手順で進められます。
現地調査:ひび割れや水の侵入箇所を確認。必要に応じて散水試験を実施。
下地処理:古い塗膜や汚れを除去。これを怠ると防水層が早期剥離。
プライマー塗布:防水材との密着性を高めるため、下地に下塗りを行う。
防水材施工:ウレタン塗布やシート貼りなど、選定工法に基づき防水層を形成。
トップコート仕上げ:紫外線や摩耗から防水層を守る保護層を塗布。
この工程を丁寧に行うことで、10年以上の耐久性を確保することができます。
防水工事は単なる雨漏り対策にとどまらず、建物全体に大きな恩恵を与えます。
建物の寿命を延ばす
カビや湿気を防ぎ、快適な住環境を維持
資産価値の保持
省エネルギー性能の向上(遮熱・断熱効果)
一方で、以下のような課題も存在します。
施工不良のリスク:下地処理不足や材料の選定ミスで短期間に劣化する可能性。
コスト負担:工法によって価格差が大きく、建物オーナーにとって費用計画が重要。
メンテナンス必須:10~15年を目安に再施工や補修が必要。
近年、防水工事の分野にも革新が進んでいます。
IoTセンサーの導入:防水層内部の湿度や浸水をリアルタイムで監視。
自己修復型防水材:小さなひび割れを自動で塞ぐ新素材が開発中。
環境対応型工法:水性塗料やリサイクル材を使った環境配慮型工法が普及。
災害対策防水:地震や洪水に耐える柔軟性・強靭性を兼ね備えた防水材が登場。
防水工事は「建物を水から守る」だけでなく、耐久性・資産価値・快適性・環境性能を維持するために欠かせません。
今後はIoTや新素材の進化により、防水工事はより高性能・省エネ・持続可能なものへと進化していくでしょう。
建物を長く安全に使うためには、適切な工法の選択、丁寧な施工、そして定期的なメンテナンスが不可欠です。
次回もお楽しみに!
増田工業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っている
増田工業、更新担当の富山です。
目次
防水工事とは、建物内部に雨水や地下水が侵入するのを防ぐための施工を指します。
屋根、屋上、ベランダ、外壁、地下室、浴室といった、水の影響を受けやすい部分に行われ、建物の寿命や安全性を大きく左右します。
特に日本は四季があり、梅雨や台風、大雪など気候変動も激しいため、防水性能の確保は建築物にとって最重要課題の一つです。
建物に水が浸入すると、内部の木材や鉄筋が腐食・錆びを起こし、建物強度が低下します。
さらに室内環境にカビや湿気をもたらし、住環境の悪化や健康被害を招く恐れもあります。
また、漏水による修繕費用は膨大になる場合があり、初期の防水工事や定期メンテナンスを適切に行うことが、結果的にコスト削減につながります。
古代メソポタミアやエジプト文明では、アスファルトや粘土が防水材として利用されていました。
日本でも漆や柿渋など自然素材を活用した簡易防水が行われてきました。
現代ではウレタン防水やFRP防水、シート防水など、科学技術の進歩によって高性能な工法が普及しています。
建築基準法および関連する法規定では、建物の安全性と耐久性を確保するため、防水性能の維持が義務付けられています。
特に以下の点が重要です。
屋上や屋根の防水:降雨時に大量の水が集中するため、浸水防止措置が必須。
地下構造物の防水:地下水や地盤水位の影響を受けやすく、耐水設計が厳格に定められている。
バルコニー・ベランダの防水:共用部分であり、雨漏りが室内や下階に影響するため規制が強い。
これらの基準は、建築確認申請や竣工検査でもチェックされ、不適合があれば使用許可が下りない場合もあります。
防水工事が必要となる部位は建物全体に及びますが、特に以下の箇所が重点対象です。
屋上:最も雨水の影響を受けやすく、劣化が進みやすい。ウレタン防水やシート防水が主流。
ベランダ:日常的に雨水が溜まりやすいため、FRP防水など耐久性の高い工法が適用される。
外壁:ヘアクラック(細かいひび割れ)からの浸水を防ぐため、塗膜防水やシーリング工事が行われる。
地下室:地盤の水圧や湿気対策として、セメント系防水やアスファルト防水が用いられる。
浴室・水回り:水を常に使用するため、完全な防水層が不可欠。特殊な防水シートや防水モルタルを施工する。
部位ごとに適切な工法を選ぶことが、建物の健全性を守る最大のポイントです。
ここまで、防水工事の基礎知識、建築基準法との関係、そして施工対象の概要を紹介しました。
防水工事は「目に見えにくい裏方の工事」ですが、実は建物の寿命や安全性を左右する極めて重要な工種です。
次回は、具体的な工法の種類、施工手順、そして将来の展望についてさらに掘り下げてご紹介します。
次回もお楽しみに!
増田工業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っている
増田工業、更新担当の富山です。
目次
前回は「やりがい」についてお話ししましたが、今回は、防水工事という仕事の長期的な魅力やこの業界で働くことの価値についてお話します。
戸建て住宅・マンション・商業施設・公共インフラ・学校・病院――
防水が必要ない建物は、存在しません。
つまり、防水工事は社会に絶対に必要とされ続ける仕事です。
時代がどれだけ変化しても、雨は降り続けるし、建物は防水がなければ持ちません。
景気に左右されにくい安定性があるのも、この仕事の魅力のひとつです。
防水工事は、材料の扱い方や施工の手順、現場管理など、現場経験の積み重ねで技術が磨かれていく職種です。
一度技術を身につければ、全国どこでも、年齢を重ねても活躍できるチャンスがあります。
「手に職がある」安心感は、これからの不安定な社会を生きるうえで、何よりも大きな武器になります。
防水工事は、目立たない仕事でありながら、直接的に人の命や暮らしを守る役割を担う工事です。
自分がつくった防水層が、10年・20年と機能し続けていると思うと、ものづくりの喜びと責任を同時に感じられます。
しかも、建物が建つ限り、新築・改修を問わず工事の需要は尽きません。
一つひとつの現場に“意味”があるという点で、この仕事はとても誇り高いものです。
防水技能士、防水施工管理士などの資格を取得すれば、施工だけでなく現場監督や管理者へのキャリアアップも可能です。
将来的には独立して、自分の会社を持つ職人も少なくありません。
長く続けるほどに選択肢が増えていく職種でもあり、“一生ものの仕事”にできるのが、防水工事の真の魅力だといえるでしょう。
今、防水業界は若い人材の参入を必要としています。
新しい防水技術もどんどん進化しており、IoTを使った防水の劣化診断や、環境対応型の材料開発など、次世代の防水職人が活躍できる舞台は着実に広がっています。
防水工事は、派手さはなくても「なくてはならない仕事」。
人々の暮らしと建物を守り、社会のインフラを支える、まさに職人魂の光る仕事です。
この仕事を通して、「誰かの安心を生み出す」実感を、あなたもきっと味わえるはずです。
次回もお楽しみに!
増田工業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っている
増田工業、更新担当の富山です。
目次
建物の“縁の下の力持ち”とも言える防水工事。
今回は、そのやりがいについて、現場の声を交えながら深掘りしてご紹介します。
防水工事は、外から見て「目立つ」ものではありません。
屋上、ベランダ、バルコニー、地下構造物の防水層は、完成してしまえば普段は意識されることもない部分です。
しかし、この防水層がしっかり機能していなければ、雨漏りや腐食、カビなど、建物全体の寿命や安全性を著しく損なうことになります。
つまり、防水工事は**「見えないけれど、人の暮らしを根底から支えている仕事」**なのです。
この“縁の下”の役割こそが、多くの職人にとってやりがいに繋がっています。
防水工事は、作業中の気温・湿度・乾燥時間・材料の混ぜ方・施工順序など、細かい条件の管理が求められます。
防水層に小さな気泡が混じっただけで、数年後に漏水を引き起こす可能性すらある、“見えない精度”を求められる現場です。
だからこそ、1ミリ単位で丁寧に仕上げ、10年後も「雨が漏れてこない」ことにこだわるプロ意識が必要とされます。
完成した防水層の上を歩いたとき、「あ、これは自分の手でしっかり守った場所だ」と実感できる瞬間が、職人にとって最高の達成感となります。
雨漏りが止まったとき、お客様が心から安心した表情で「ありがとう」と言ってくれる瞬間は、この仕事をしていて一番嬉しい場面です。
特に、長年悩んでいた住宅の漏水を止めたときや、台風・豪雨に備えた補修工事を終えた直後の安心感は、言葉では表現できないほどです。
「また雨が降っても大丈夫」と思える日常を取り戻す手助けができること――
それが、防水工事の大きなやりがいです。
一人ではできない仕事。それが防水工事。
協力業者や設計者、現場監督と綿密に連携しながら、一つの現場を仕上げていく「チームワーク」もこの仕事の魅力です。
現場が完了したときの、チーム全員での「お疲れさまでした!」というひと言。
その達成感は、机の上では味わえない、現場仕事ならではの感動です。
次回は、「防水工事の魅力」について、もう少し視野を広げてお話しします。
次回もお楽しみに!
増田工業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っている
増田工業、更新担当の富山です。
目次
今回は「防水工事の未来」についてお話しします。
どんな仕事も、時代とともに進化していきます。防水工事も例外ではありません。今はまだ人の手が中心の仕事ですが、技術や社会の変化に合わせて、どんどん変わっていこうとしている最中なんです。
現在、防水工事の現場でも課題になっているのが、職人さんの高齢化と若手の減少。
昔ながらの“手塗り”“手張り”といった技術は、非常に大切ですが、同時に「覚えるのが難しい」「体力的にキツイ」と感じる若い人も多いのが現状です。
そこで今、注目されているのが…
✅ 作業の機械化・省力化
✅ スマホやタブレットを使った施工管理
✅ オンライン動画やVRでの研修・技術継承
昔ながらの良さを活かしながらも、“今どきのやりやすさ”を取り入れる未来型の防水工事が求められているんです。
防水材も、どんどん進化しています。
📌 遮熱・断熱効果のある防水材 → 夏の室温上昇を防ぎ、電気代削減へ
📌 自然素材系のエコ防水材 → バイオ由来で地球にもやさしい
📌 自己修復型の防水材 → 小さな傷がついても自分でふさがる驚きの性能!
こうした“ハイテク防水材”が、これからの住宅やビル、倉庫などのスタンダードになっていく可能性が高まっています。
これからの建築は「スマート化」がキーワード。AI・IoTといった技術を使って、建物の状態を24時間チェックしたり、自動的に補修を行ったりするような時代が来ています。
防水工事もそこに参加しています。
ドローンによる屋上点検
センサー付き防水層で劣化を自動通知
データと連動した「予防メンテナンス型防水」
今までは「漏れてから直す」だったものが、**「壊れる前にケアする」**方向に変わっていくのです。
これからの防水工事は、こうなっていくはずです:
職人さんにとって「働きやすい現場」
地球にやさしい「エコな素材」
ご近所さんにも気を配った「静かでにおわない作業」
お客さまにとって「早くて長持ちで安心な施工」
防水工事は、見えないけれど建物にとって本当に大切な仕事。
そしてその現場も、人にも環境にも、未来にもやさしく変わっていこうとしています。
昔ながらの技術と、これからの新しい工夫が一緒になれば、もっと魅力ある仕事にきっとなっていきます。
これから防水工事を頼もうとしている方も、現場で働く方も、未来に向けての一歩を楽しみにしていただけたらと思います!
次回もお楽しみに!
増田工業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っている
増田工業、更新担当の富山です。
目次
今回は、防水工事が関係する“環境問題”についてのお話です。
「防水工事って、屋上とかベランダをきれいに塗る作業でしょ?それが環境とどう関係あるの?」と思うかもしれません。でも実は、防水工事も自然や街の空気、水、人との関係と深くつながっているんです。
まず注目されるのが、防水工事に使われる「材料」。
代表的なものには、ウレタン防水、FRP防水、アスファルト防水、シート防水などがありますが、その中には溶剤系(油性)のものも多く含まれています。これらの材料は、施工時に揮発性有機化合物(VOC)を発生させ、大気汚染や健康への影響が懸念されることもあるんです。
ウレタン系塗膜防水の一部にはシンナーなどの有機溶剤が含まれ、施工時に強い臭気を発する
FRP防水の施工では樹脂の硬化剤による化学反応で刺激臭や粉塵が発生する
洗浄水や廃液の処理を誤ると、排水や土壌への影響も
現場では、こうした影響をできるだけ減らすために、職人さんたちはいろんな工夫をしています。
✅ たとえば…
低VOC、無溶剤タイプの防水材を使用する
飛散防止のため、風の強い日の施工を避ける
使用後の器具洗浄水は回収して専門業者に処理を依頼
においの強い作業前には、近隣住民にあいさつや説明をする
「ただ塗るだけ」ではなく、“人にも環境にもやさしい現場”をつくる努力が今どんどん求められているんです。
防水工事は、建物を守るだけではなく、都市全体の環境保全にも貢献しています。
たとえば…
雨水の侵入を防ぐことで、カビや湿気の発生を抑え、室内の空気環境を清潔に保つ
適切な防水で建物の寿命を延ばし、資材や建て替えによる廃棄物を減らす
遮熱防水などの断熱性能向上によって、空調エネルギーの節約にもつながる
こうした地味だけど確実なエコ活動が、防水工事の現場で日々行われているんです。
「防水工事=環境に悪い」ではなく、「どうすれば環境にも配慮した防水工事ができるか」が、これからの時代の大切なテーマです。
材料の選び方、作業の仕方、ご近所への気配りまで──
それら全部が、“未来にやさしい現場づくり”につながっています。
次回は、防水工事のこれからの未来像について、もう少し掘り下げてお話していきます!
次回もお楽しみに!
増田工業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っている
増田工業、更新担当の富山です。
さて今回は
~鉄則~
ということで、今回は防水工事を確実に成功させるための「鉄則」について、「施工計画」「材料の選定」「下地処理」「施工精度」「品質管理」「メンテナンス」などの観点から詳しく解説します。
防水工事は、建物を雨水や湿気から守り、長期間にわたって安全で快適な環境を維持するために不可欠な工事です。
屋根、ベランダ、外壁、地下構造物など、あらゆる箇所に適切な防水施工が求められます。
しかし、防水工事には適切な材料の選定、正しい施工方法、徹底した品質管理が必要であり、これらが守られないと漏水や建物の劣化につながるリスクがあります。
目次
防水工事では、施工場所や環境に応じた最適な工法を選ぶことが重要です。適切な工法を選ばないと、防水層が劣化しやすく、漏水のリスクが高まります。
✅ 屋上・陸屋根 → ウレタン防水・シート防水が主流
✅ ベランダ・バルコニー → ウレタン防水・FRP防水(耐摩耗性が高い)
✅ 地下構造物(ピット・外壁) → アスファルト防水・塗膜防水・シート防水
✅ 外壁 → 透湿防水シート・シーリング防水
✅ プール・水槽 → FRP防水・セメント系防水(防水性能+耐水圧)
施工場所や用途に応じて、耐久性やメンテナンス性を考慮した工法を選ぶことが鉄則です。
防水工事には様々な材料が使用されますが、気候条件、使用環境、耐用年数などを考慮して選定する必要があります。
✅ ウレタン防水(塗膜防水)
✅ FRP防水(ガラス繊維強化プラスチック)
✅ アスファルト防水(シート防水)
✅ シート防水(塩ビシート・ゴムシート)
✅ 寒冷地・降雨が多い地域 → 低温硬化型のウレタン防水が有効
✅ 耐久性重視 → FRP防水やアスファルト防水を選択
✅ 軽量化が求められる屋根 → シート防水を採用
材料選びを誤ると、施工後のトラブルにつながるため、長期的な視点で耐久性を考慮することが鉄則です。
防水工事の仕上がりや耐久性を左右するのが「下地処理」です。下地が適切に処理されていないと、防水層が浮いたり剥がれたりする原因になります。
✅ 汚れ・ホコリの除去 → 表面に汚れがあると、防水材が密着しない
✅ クラック(ひび割れ)の補修 → ひび割れがあると、そこから水が浸入する
✅ 水分量の確認 → 乾燥が不十分な状態で施工すると、防水層が膨れる
✅ コンクリート下地 → プライマー処理で吸水を防ぐ
✅ 金属下地 → 防錆プライマーを塗布
✅ 木造下地 → FRP防水や防水シートで補強
「下地処理を怠ると防水工事の成功率が下がる」という意識を持つことが鉄則です。
防水工事では、施工時のムラや塗布量の不足が防水効果の低下につながるため、施工精度を高めることが重要です。
✅ ウレタン防水の標準塗布量:1.5〜2.0kg/㎡
✅ FRP防水の樹脂厚み:2.0mm以上が推奨
✅ シート防水の接着面積:100%確保
「適正塗布量を守る=防水性能の確保」と心得ることが鉄則です。
✅ 温度・湿度を管理し、適切な乾燥時間を確保する
✅ ローラーやコテの均一な使い方を意識する
✅ 重ね塗りを均等に行い、膜厚を一定にする
✅ 塗膜の厚みを計測し、基準値を満たしているか
✅ 防水層の浮き・剥がれがないか目視検査
✅ 防水層の水密性を確認するための漏水テストを実施
✅ 5年ごとに点検を行い、防水層の劣化を早期発見
✅ トップコートの再塗装を行い、紫外線劣化を防止
✅ シーリング材の劣化確認を実施し、補修対応
✅ 適切な防水工法と材料を選定する
✅ 下地処理を徹底し、防水材の密着性を確保する
✅ 施工精度を高め、適正な塗布量を守る
✅ 品質管理とメンテナンスを継続し、防水性能を維持する
これらの鉄則を守ることで、長期間にわたって漏水を防ぎ、建物の寿命を延ばす高品質な防水工事が実現できます。
次回もお楽しみに!
増田工業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っている
増田工業、更新担当の富山です。
さて今回は
~歴史~
ということで、今回は防水工事の歴史を深く掘り下げ、古代から現代に至るまでの技術の変遷、背景、そして未来の展望について詳しく解説していきます。
建築物において「防水工事」は、建物を雨水や湿気から守り、長期間にわたって安全で快適な環境を維持するために不可欠な技術です。
古代の文明から現代に至るまで、防水技術の進化は建築の発展と密接に関わってきました。
目次
世界最古の防水技術の一つは、古代メソポタミア文明(現在のイラク周辺)で発展しました。
✅ 天然アスファルトを建築材料として使用
この技術は後の防水工事の基礎となりました。
✅ 石灰や粘土を活用した防水技術
✅ 火山灰(ポゾラン)を活用した「ローマン・コンクリート」
この技術は現代の防水モルタルの原型とされている。
✅ ゴシック建築の屋根防水
✅ 城や要塞の防水対策
✅ アスファルトと防水工事の発展
✅ 鉄筋コンクリートの登場(19世紀末)
✅ レンガ建築と防水技術
✅ 関東大震災(1923年)後の耐震・防水技術の向上
✅ 高度経済成長期(1950〜1970年代)の建設ラッシュ
✅ 最新の防水技術
✅ 環境配慮型の防水技術
今後、防水工事はさらに進化し、環境負荷の低減とメンテナンスの簡易化が求められるようになります。
✅ 自己修復型防水材の開発
✅ AIとドローンを活用した防水点検
✅ 防水材のさらなる高耐久化
✅ 古代メソポタミアのアスファルトから始まり、ローマ時代に防水コンクリートが発展。
✅ 産業革命以降、アスファルトやシート防水が普及し、日本でも高度経済成長期に技術が発展。
✅ 現代では環境配慮型の防水技術やAI診断技術が導入されている。
防水工事は、これからも進化し続け、建築の安全性と持続可能性を支える技術であり続けるでしょう。
次回もお楽しみに!
増田工業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
皆さんこんにちは!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っている
増田工業、更新担当の富山です。
本日は第6回防水工事雑学講座!
今回は、防水工事と環境への配慮についてです。
サステナブルな防水工事の取り組み
今の時代、どんな業界でも環境への意識が高まっていますよね。
防水工事も例外ではありません。
地球に優しく、そして建物にも優しい防水工事を目指すために、新しい材料や技術がどんどん開発されています。
このシリーズでは、環境に配慮した防水工事の取り組みについて、解説していきます!
環境に優しい材料の活用
防水工事では、使用する材料にも大きな進化が見られます。
「防水材」というと、なんだか化学薬品っぽいイメージを持つ方もいるかもしれませんが、今は環境への影響を抑えたエコな材料が増えているんですよ。
1. 低VOC材料の活用
「VOC」って聞いたことがありますか?
VOC(揮発性有機化合物)は、従来の塗料や接着剤などに含まれている成分で、揮発すると大気汚染の原因になることがあります。
環境に優しい防水工事では、このVOCの排出を抑えた「低VOC材料」が使われています。
どう違うの?
低VOC材料は、有害物質の排出を最小限に抑えているため、施工する人の健康にも配慮されています。
また、使用後も大気への影響を減らすことができるんです。
どんなところで使われている?
特に、屋上防水や外壁防水で活用されることが多く、学校や病院など環境配慮が重要な施設でも選ばれています。
2. リサイクル可能な防水材
もう一つ注目したいのが「リサイクル可能な防水材」です。
通常、防水工事で使った材料は廃棄されることが多いのですが、最近では、廃材をリサイクルして新しい防水材に再利用する仕組みが進んでいます。
どんな効果があるの?
廃材を減らせることで、ゴミの削減につながります。また、資源の再利用が進むことで、材料を作るときのエネルギー消費も減らせるんです。
エピソード
ある施工現場では、古い防水層を取り除いた廃材をリサイクル工場に送り、新しい防水材として再利用したそうです。
「ただ防水するだけじゃなくて、地球の未来も考えた工事ができた」とスタッフの方もやりがいを感じたとか。
断熱性向上で省エネ効果も!
防水工事は「雨漏りを防ぐ」だけじゃないんです。
実は、建物の断熱性能を高めることで、省エネにも貢献できるんですよ。
暑い夏でも涼しく、寒い冬でも暖かくする工夫が詰まっています。
1. 断熱材の導入
防水工事の際、屋上に断熱材を組み合わせると、断熱性能が格段にアップします。
これにより、外気の影響を受けにくくなり、室内温度が快適に保たれるんです。
夏はどうなる?
直射日光を遮り、建物が熱を吸収しにくくなるため、エアコンをガンガン使わなくても涼しく過ごせます。
冬はどうなる?
屋内の暖かさを外に逃がさないので、暖房の効率が良くなり、少ないエネルギーで暖かく過ごせます。
2. 冷暖房費の節約
断熱性能が上がると、直接的に「お財布に優しい」というメリットもあります。
冷暖房の使用を抑えられるので、電気代やガス代が節約できるんです。
具体的な効果は?
ある住宅で屋上防水工事に断熱材を導入したところ、冷暖房費が年間で約15%削減されたというデータも。
少しの工夫でこれだけ変わるのは嬉しいですよね!
エコな暮らしへ
省エネが進むと、地球環境にも優しくなります。
温室効果ガスの排出量を減らし、サステナブルな暮らしをサポートしてくれる防水工事、魅力的ですよね。
地球にも建物にも優しい防水工事を選ぼう
防水工事は、建物を守るだけでなく、環境や私たちの暮らしをもっと快適にしてくれる可能性を秘めています。
「低VOC材料」や「リサイクル可能な防水材」は、環境への配慮を欠かさず、地球に優しい工事を実現します。
また、断熱性を高めることで、省エネ効果と快適な暮らしの両方を手に入れることができます。
これからの防水工事は、建物の未来と地球の未来を一緒に守るものへと進化していきます。
あなたのお家でも取り入れてみませんか?
次回も、役立つ防水工事の情報をお届けしますのでお楽しみに!
増田工業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
熊本県熊本市を拠点に防水工事を行っております。
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()